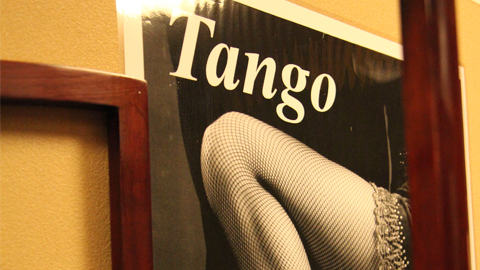皆さん、こんにちは!池袋のアルゼンチンタンゴ教室『タンゴレアル』です。
前回は、初期のマテ茶器である「ひょうたん」に宿る温もりについてご紹介しました。今回はその続きとして、マテ茶を飲む上で欠かせないもう一つの大切な道具、「ストロー(ボンビージャ)」の歴史に触れてみたいと思います。特に、初期に使われていた「竹筒」のボンビージャに焦点を当て、人と自然がどのように繋がっていたのかを探ります。
初期のストロー:竹筒が繋ぐ人と自然
マテ茶を飲む際に使う金属製のストロー「ボンビージャ」。実は、そのルーツは自然の素材、特に「竹」にありました。素朴ながらも、当時の人々の知恵と自然への敬意が詰まった竹筒のボンビージャは、現代に生きる私たちにも大切なメッセージを伝えてくれます。
リオス先生のコレクション紹介:初期の竹でできたストロー(ボンビージャ)
『タンゴレアル』のリオス先生は、マテ茶器だけでなく、初期の竹製ボンビージャも大切にコレクションされています。一つひとつ手作業で作られたであろう竹筒は、節の形や太さが異なり、それぞれに個性があります。使い込まれた竹の表面からは、かつて多くの人々の手に渡り、マテ茶と共に時間を過ごしてきた歴史が感じられます。
竹がストローとして使われていた理由、自然素材の良さ
なぜ竹がボンビージャとして選ばれたのでしょうか?それは、竹が南米の豊かな自然の中で手軽に入手でき、加工しやすい素材だったからです。竹は軽くて丈夫、そして何よりも自然の恵み。当時の人々は、身近にある素材を最大限に活用し、生活に役立てていました。竹製ボンビージャは、自然の素材が持つ温かみや、口当たりの良さも魅力です。
竹製ストローの使い方、お手入れ方法など
竹製ボンビージャの使い方は、現代の金属製ボンビージャと基本的には同じです。マテ茶の葉が口に入らないよう、先端にフィルターの役割をする部分が付いています。お手入れは、使用後に水でよく洗い、しっかりと乾燥させることが大切です。自然素材ゆえに、カビが生えないよう風通しの良い場所で保管するなど、少し手間をかけることで、長く愛用することができました。
現代のストローとの比較、サステナビリティへの意識
現代では、ステンレス製など様々な素材のボンビージャが主流ですが、初期の竹製ボンビージャからは、当時の人々の「ものを大切にする心」や「自然との共生」の精神が伝わってきます。使い捨てが当たり前になった現代において、自然素材を活かし、長く使うという知恵は、私たちにサステナビリティ(持続可能性)について考えるきっかけを与えてくれます。
マテ茶の文化を通じて、南米の豊かな自然と人々の暮らし、そしてそこから生まれた知恵に触れることは、日々の生活に新たな視点をもたらしてくれます。
タンゴもまた、自然な体の動きと、人との繋がりを大切にするダンスです。竹筒のボンビージャが自然と人を繋いだように、タンゴはあなたと新しい世界を繋ぐ架け橋となるでしょう。
「動けるからだ」を作り、心も体も豊かになるアルゼンチンタンゴを、私たち「タンゴレアル」で始めてみませんか?ダンス未経験の方も、50代から始める方も大歓迎です。
皆様のお越しを心よりお待ちしております。
検索キーワード: #マテ茶ストロー #竹 #自然素材 #南米の知恵




-1-e1755164829227-456x276.png)